上坂冬子『生き残った人々』
上下、文藝春秋、1989
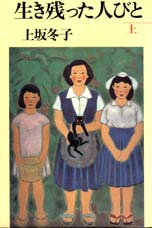
平山郁夫画伯の東京美術大学の卒業制作「三人姉妹」より
三人の女性の衣服、わら草履、木製のサンダル、下駄の鼻緒、これらが在アメリカの被爆者たちとオーバーラップしたと著者は書いている。平山画伯も広島出身で被爆者であるとか。
著者は1987年『奄美の原爆乙女』(中央公論社)を出版したあと、一通の航空郵便を受け取った。差出人は日系アメリカ人メリー藤田で、アメリカにも被爆した日系人が千人ほどいるので、ぜひ取材してほしいという依頼状であった。著者はその依頼を受けて米国に向かうのである。アメリカが落とした原爆によって、後遺症に苦しみながらひっそりと暮らしている日系人がアメリカに千人もいたということは驚きである。それは広島が日本で最も多くの移民を送り出した県であることと関連がある。
上下卷の中に様々な被爆者の人生が描かれている。これだけではまだ書ききれないかのように、様々な人生が紹介されている。人の生き方はさまざまである。共通なのは過去のある時点で、“そのとき何かがピカッと光った”ことに始まる。奇跡的に一命をとりとめても、後遺症を引きずってその後を生きていくことになる。
航空郵便を送った当の人、メリー藤田は1908年広島生まれで、16歳のときアメリカに渡る。排日法といわれた移民割当法が制定され、日本人の受け入れが制限される直前である。5歳年上の夫も広島生まれで、移民の子として年内なら渡米可能のぎりぎりのときに、親同士の決めた結婚に従う。
夫は牡蠣の養殖事業で成功するのだが、仕事中の事故で障害者となる。
妻は前向きに生きようとして、美容師の資格を取り、夫、一人息子とともに帰国、日本で美容院を開業する。これがアメリカ帰りのパーマネントとして大当たりした。夫はハーレーダビットソンを乗り回していたが、妻は広島の市電に乗り帰宅する途中、何かがピカッと光った。気がついたとき彼女は電車から振り落とされ路上に横たわっていた。爆心地から2キロの地点である。その電車のひとつ前の電車に乗る予定だったにもかかわらず、その電車は彼女の存在に気づかず素通りしていった。もしそれに乗っていたら爆心地に近いところで被爆していたに違いない。
あたりは火災が発生し地獄絵が展開している。この体験を後にアメリカで機会を見つけては話し続けるのである。
幸いに息子のジーンは生きて帰宅した。しかし夫は待てども帰宅しなかった。懸命に夫の姿を探し回る。夫の出かけていた場所の見当はついていたので、その方角に出向き、たくさんの遺体の中に夫の姿を求めた。ついにハーレーダビットソンが赤く焼けたまま立っているのを見いだすことになった。
「その快活な表情とうらはらに、メリー藤田の体の芯の部分には焼け野原であてもなく夫の骨を探した体験が埋もれているのだった。」やがて髪が抜けたり、ブラブラ病という被爆者特有の病気に悩まされる。
戦後になってアメリカ生まれの息子は米国籍であることを利用して渡米。それを追う形で、母親も再びアメリカに旅立つ。ひとえにアメリカののびやかな空気が吸いたかったという。しかし、息子は朝鮮戦争に従軍しなければならなかった。
彼女自身は生活をしていく上での才覚には恵まれていたようである。ボランティア活動では敬老ホームの老人たちへの美容サービスが受けていたようだ。さらに被曝体験談の巡回サービスを長年続け、米国原爆被害者協会の西北アメリカの支部長を務めていた。「生き残った人々」のやるべき活動に生きがいを感じていたに違いない。
(2007.12.20) (2017.04.01) 森本正昭 記