新潮社、1980
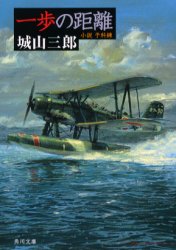
角川文庫より
副題に「小説予科練」とある。主人公たちは予科練の練習生で、年齢は15歳から16歳である。
「全員眼を閉じよ。よく考えた上で、志願するものは一歩前へ」
志願するのは必死必中の兵器(人間魚雷)の搭乗員になること、いずれ死ぬとわかっていても、突然それを要求された時には、あまりにも大きな決断をしなくてはならない。それは無限に長い時間に思えた。前に出るのも出ないのも、勇気が要る。よく考えてと言われても、考える余裕はない。一歩の前と後には、眼もくらむばかりの底深い谷があったと著者は述べている。
主人公・塩月にとって一歩の距離は遠かった。前に出なかったのだ。そのため彼はそのときのためらいを罰せられていると感じるようになる。前に出た同僚は一様に晴れやかな表情をしている。
敗勢の濃い終戦の年、飛行機が一機もない航空隊で、毎日は陸戦訓練しかない。予科練に志願するときから、空以外での死を考えたことはなかった若者にとって辛い日々であった。この小説ではこの一歩の試練があった後、同僚訓練生の個々の家庭の事情が詳しく描かれていて、この小説を読み応えのあるものにしている。
飛行機のない航空隊での訓練とは、上官の暴力に耐えることだったのか。
「きさまたちは消耗品(スペア)、消耗品は消耗品」というや、バッター(棍棒)で殴られる。バッターとは軍人精神注入棒と呼ばれたしごき棒のことである。日露戦争以来の伝統である。帝国海軍にあって列国海軍にないものはバッターだといわれていた。これに殴られているうちに、何かが鍛えられるのか。そんな気がしてくるとしても、それは逃げ道のない自己催眠にかかっているだけなのだが。
どんなときに殴られるのか。平等に殴られるのかというと、殴りたい顔つきをしている者は、集中的に棍棒を浴びたという。上官は一人で全員を殴ると手を痛めるため、向き合っている仲間同士を殴らせる。ついに同僚の古手川が殴り殺されるにいたる。古手川が予科練を志願した事情や特攻を志願した事情が詳しく描かれていて痛ましい。
階級の低い者を殴るのは、戦闘場面にあって上官の命令に有無を言わさず従わせるための手段と考えられていたのだが、これが強い軍隊を育てる唯一の方法だったのだろうか。むなしく、そして切ない。
(2007. 7. 6)
新潮社、1980
百式司令部偵察機

ウィキイペディアより借用しています
日本陸軍の主力偵察機で、当時は630km/Hの高速を誇っていた。
8つの小品に分かれているが、それぞれが異なる戦闘機の機種の解説に始まる。ここで紹介するのは「赤い夕日」という小品で、有名な百式司令部偵察機が紹介され、それにまつわる話が展開している。そして8つの小品はどれも戦中と戦後を比較するかのように語られている。
戦前戦中において日本の一部の若者があこがれ、ユートピアを夢見ていたのは当時世界で唯一の社会主義国ソ連であった。ときの政府の烈しい弾圧の下で、彼らはマルキシズムを実現した国へのあこがれを抱いていた。先端思想であると感じたせいであるし、日常の強制的な皇国主義的教育への反発のせいであったかと思われる。
主人公・村尾が軍事教育を終えた後の赴任先は満州であった。
「4000年の悠久の土壌の上に、北からは新しい時代の風がにおってくる。あらためて考えてみると、満州は願ってもない任地といえた。その広漠たる大地には、自分を見直しつくり直す機会が、海のようにひろがっている気がした。」
「それに空は高く大きく、地平線まで何ひとつ眼を遮るものもない大陸の風景が、村尾をよろこばせた。満州に来てよかったと村尾はあらためて思った。」
「飛行場は、海のような草原のただ中に在った。草原をまっすぐまっすぐ北へ行き果てれば、川があり、川ひとつ越すと、社会主義の国がある。かつては観念の中でだけ存在していたユートピアが、すぐ先に在ると思うと、村尾の中の思想が水でもふくんだように息づいてきた。」
新司偵は、すばらしい飛行機であった。強力な二基のエンジン、軽快な曲線の機体、比べもののない高速。それは満州の大空を飛行するにはまさにぴったりの飛行機であった。村尾はこの飛行機に乗っての亡命を考えた。このような兵隊が本当にいたのかどうかわからないが、まだ見ぬ理想郷への脱出は若者をかりたてる。上官の目を盗んでは、在満活動家をしばしば訪問し情報交換をする。その意図はついに見破られて逮捕されてしまうことになった。
そんなとき、かつて所属していたチチハルの部隊の消息が気がかりになる。誰一人生きて還ったという話を聞かないところから生き残ったのは自分だけだと知ることになる。
戦争があったから、戦後があるのである。村尾の活動は若い活動家とは相容れないし、彼らを見る目はひとり異質であると感ずるようになっていく。
(2007. 7 .7)

東京日々新聞
(昭和12年12月9日)
『決定版昭和史』 毎日新聞社より
先の戦争ではメディアといえば新聞とラジオにかぎられていた。国民は開戦の報道をむさぼるようにして見聞きした。小学生であった私が体験したのは新聞の紙面がしだいに薄くなっていき、終戦時にはペラ一枚になったことだった。
この本を読んだ後のイメージは次のようなものである。
新聞社の編集局、おびただしい資料や書籍、新聞が渦高く積まれている。ここで仕事をしている男が三人と手持ちぶさたながら、いかめしい表情の軍人が一人部屋の中を歩き回っている。
一人は懸命に社説の原稿を書いている。以前は軍部批判の社説が多いので要注意とされていた。いまでは軍部に協力的な社説ばかりを書いている。当時の新聞は言論取締法規によってしばられていた。整理部員は日夜、時間に追われながら、紙面の整理、編集を行い、分厚い命令綴りで記事が引っかからないよう目を皿にしてチェックしていた。違反すれば、発売頒布禁止とされてしまうからだった。
二人目はどうやら宣伝班の人らしい。軍国美談を編み出すことはないかと頭をひねっている。さらに戦意高揚のため、銃後のキャンペーンとして軍歌や唱歌を国民から募集する仕事をしている。銃後の花、進軍の歌、小国民愛国歌などが流行した。
三人目はこの新聞社の要職にある人で、いつも手にソロバンを持っている。全国の発行部数の推移や収支の計算に余念がない。なにしろ戦争ほど新聞発行に影響力の強いものはない。新聞は自国民にとっての最大のニュースである。それがたとえ軍部による謀略によって作り上げたものであっても無条件で即追認する結果となっていった。軍国主義、愛国心、排外的ナショナリズムをあおれば収入が上がり、社員の生活がうるおった。
軍人はいつも居丈高で、いらいらしながら部屋中を歩き回っている。仕事ぶりが軍部の気に入らないと軍刀を抜かんばかりの勢いで新聞社を威かす役割なのだ。しかしやがて軍部と新聞の二人三脚は進み、新聞の協力ぶりに百点満点をつけ感謝状を贈るに到る。
事実はどうであったかというと、新聞業界全体は、満州事変以後、販売部数は大きく伸びて黄金時代を迎えていた。軍の暴走におののきながら、その反動としてのエロ・グロ・ナンセンスが収入源になっていた。軍部への協力を拒絶すれば、新聞紙の割り当てが得られなかった。これには抵抗のしようがなかった。
このような状況の中で、あくまでもジャーナリストとしての信念を貫いた人もいた。本著の中では次のような事例が紹介されている。
菊竹六鼓『福岡日日新聞』は五・一五事件で軍部と正面から対決した、大新聞の商業主義優先を「新聞の魂を売った」としてきびしく批判した。菊竹は朝日と毎日が商業主義にはしり、「新聞は商品である」と唱えたことを皮肉っている。徹底した軍部批判をした。死を賭てでも、言論を守るという気概を秘めていた。
横田喜三郎は帝国大学新聞で政府の主張に反論。時事新報は連盟脱退に最期まで反対した。
東洋経済新報で石橋湛山は満蒙放棄論を展開。先見性と一貫性はひときわ光っている。
桐生悠々は信濃毎日の社説で「東京大空襲を嗤う」を書き退社に追い込まれる。その後『他山の石』を個人で創刊して最期まで戦った。
(2007.7.21)
坂口安吾 『桜の森の満開の下』坂口安吾全集5、筑摩書房、1990
青空文庫 www.aozora.gr.jp

篠田正浩監督により映画化。
女:岩下志麻、山賊:若山富三郎
(朝日新聞より)
「終戦の年の3月10日、東京は大空襲にみまわれる。その後、焼け残った桜が花を咲かせた。だが花見客は一人もいない。そのさまを坂口安吾は見ていた。風ばかりが吹き抜ける満開の桜の下は、冷気と静寂に支配されていた。安吾は、虚無の空間に魂が消え入っていくような不安に襲われる。」(朝日新聞、2006年4月6日、ニッポン人脈記より)
読者はこの文章を読み情景と安吾の心情を想像した上で、『桜の森の満開の下』を読み始めねばならない。怖ろしくグロテスクな物語の描写にうち震えるはずである。
冒頭に次のようなことが書かれている。桜の花の下に人が集まって陽気になり、酔っぱらったり、喧嘩をするなどということは江戸時代以降で、大昔は桜の花の下は怖ろしいものと思っても、絶景などとは誰も思わなかったそうである。
昔、鈴鹿峠で、花の季節には旅人はみな花の下で気が変になったという。そんな山に一人の山賊が住み着き、街道へ出て容赦なく旅人の衣装をはぎ取り人の命を奪った。女を捕まえてきては女房にした。こんなむごたらしい男でも桜の森の下へ来るとやっぱり怖ろしくなって気が変になった。
8人目の女は美しい女で、山賊はこのときから逆に女にほんろうされてしまうことになるのだった。とらえられ女房になった女たちは新しい女の命じるままに次々に殺されてしまうのだった。そのとき男は言いしれぬ不安に駆られる。その不安は何だろうと思うとそれは桜の花の下で感じる不安に似ているのであった。
女はたいへんなわがままもので、櫛、かんざし、紅、着物など贅沢の限りを尽くすのだが、やがてこんな山の中でなく都に住みたいといいだす。男は都の風がどんなものかを知らないまま都に住むことを決意するのだが、出かけるにあたって、満開の桜の花の下でじっと座っていてみたいと言うところがなかなか面白い。
都に住むと、今度は男にどの邸宅に忍び込めと言い、着物や宝石や装身具を持ち出させ、ついにはその家に住む人の首を持ってこさせるのだった。生首の数が多すぎるほど集まると、女は毎日首遊びを始めるのだった。もはや狂気の極みに達するのである。
男はこの生活にはキリがないから厭だと女の要求を拒否し、もう一度山に帰ろうとする。
男は女を背負って山道を登っていく。そのとき満開の桜の下を歩いていくと、背負っている女が鬼であることに気がつくのだ。男は全身の力を込めて女の首を絞め殺してしまうのだった。
これが桜の花びらが燦々と散る妖気あふれるクライマックスのシーンである。
という物語で、これは坂口安吾の傑作といわれている。グロテスクだが美しい物語で確かに面白い。冒頭にある東京大空襲の後、咲き誇った上野の桜からの連想であることは特筆すべきであろう。戦争とは関係ないと思っていると、実はこれが大量の殺戮をためらいもなく実行する戦争の狂態そのものであることにやがて気がつくというわけである。
(2007/7/26)
平和文化 1997

現在の首里城の一角より見た風景。
日本軍はこの地下に壕を掘り、総司令部を置いた。
近鉄の特急電車で旅行中、隣の席に座っていたのは,コギャル風の若い女性であった。車中でのお化粧など、私はあまり気にならないが、突然彼女は「どうしてそんな本読んでるのですか」と話しかけてきた。そんな本とはこの『沖縄戦学習…』である。彼女、米ニューヨーク州に留学中の日本の学生とわかる。沖縄、広島に行ったことがあり、戦争の話題となる。日本の若い人は戦争を知らなさすぎる、もっと知ろうとしなくてはならないと言った。沖縄から米軍基地をなくすことはできないのかとも言った。
この本のタイトルは彼女の関心そのものであったようだ。
全部で64ページの薄い本である。1部は「沖縄戦について考える」、2部は「証言が示す沖縄戦の真実」からなっている。
「沖縄戦を「祖国防衛戦」としてとらえ、沖縄県民の犠牲を「殉国の美談」として描いているものが少なくない。犠牲の内実を検証すれば、美談は粉砕される。米軍の虐殺は言うに及ばず、日本軍による「集団自決」の強要、食料強奪、スパイ嫌疑による虐殺など、県民犠牲の無残な実態が美談のかげに隠されている。この実態をひとりでも多くの国民に知ってもらいたい」と冒頭に書かれている。
沖縄戦は1945年3月26日から始まった。米軍が上陸したのは慶良間諸島の渡嘉敷島、座間味島。さらに4月1日に沖縄本島に上陸。航空機による爆撃、海からの艦砲射撃は激烈を究めたという。これは鉄の暴風と呼ばれ、80日間に及んだという。この米軍の攻撃よりも日本軍による防衛召集、学徒動員、住民の虐殺、自決の強要など住民の生命・財産の安全に対する配慮は一切行われなかった。
「証言」の中で特筆すべきは、沖縄本島南部にある真栄平(まえひら)という部落で、米軍の猛攻を受けた日本軍が住民避難地域に入り込み、すさまじい住民虐殺が行われた。その中で、逃げまどう住民に特別の配慮をした日本兵の一団があったという。それは北海道出身の第24師団に属するアイヌ兵士であった。彼らは身を挺して住民をかばったという。戦後になって真栄平部落にはおびただしい白骨が散乱していたというが、村民とアイヌ人によって「南北の塔」という慰霊碑が建てられた。
この本の中で唯一心温まる記述がなされている場面である。
ところで現代の若者にどのようにすれば、戦争体験を伝えることができるのだろうか。それがこのサイトのテーマであるのだが、悲惨な体験をそのままリアルに語るだけでは伝わらないと思う。この本は題名のとおり、学習が目的だからこれでよいのだが、難しいテーマである。冒頭の話しかけてきた若い女性はなぜ戦争(特に沖縄戦)に関心を持つようになったのか、もっと詳しい話を聞いておけば良かったと思う。
(2007/08/02)
講談社、1991年
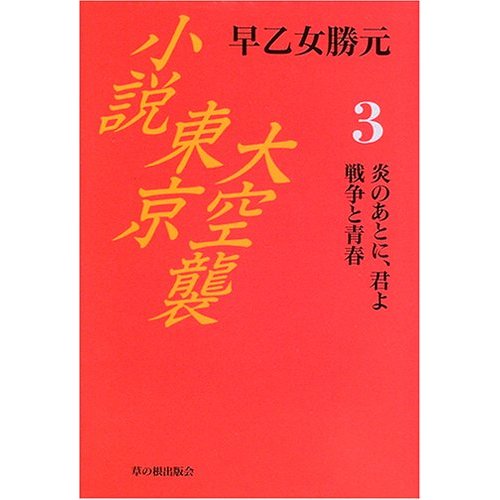
早乙女勝元
『小説東京大空襲』、草の根出版会、2005
空襲下の炎の色を表紙に表現したのかと思うが、私の体験した焼夷弾攻撃の色はこれとはかなり違う色だった。
物語は戦争を知らない世代に東京大空襲の悲劇を知らせようとする試みではないかと思う。公園のわきに忘れ去られたかのように一本の棒杭(ぼうくい)が立っている。公園といっても児童公園ほどの小さな公園。その棒杭は東京大空襲で焼け残ったものである。高さ3メートルくらいの昔なじみの電柱である。片面を焼かれざっくりとえぐられており見る影もない。近く取り去られる運命にある。この電柱がこの物語の中心である。傍らにあるベンチに毎日座りに来る一人の老女がいる。老女はいつもその電柱のあたりに視線を置いている。そして独り言のように、‘ほぅほぅほーたるこい’の「蛍の唄」を歌っている。
東京大空襲の夜の体験がこの電柱に隠されていて読者は、その老女と家族の身の毛もよだつ体験にうち震える。ここでそのストーリーを解説することははばかられる。なぜなら推理小説の謎解きの答えを教えてしまうのと同じで、著者に対してあまりに失礼だからである。その老女は願いがかなわぬまま亡くなってしまうのだが、物語の悲劇性はその先にもあり、読者の胸をえぐる。それもここで説明するわけにはいかない。読者は最後の最後まで読んでいただきたい。
早乙女氏は一般市民の戦争体験をつぶさに伝える小説や国内外の戦禍の地を訪ね歩いたルポルタージュで知られる。また東京大空襲・戦災資料センターの初代館長を務めている。東京大空襲の語り部といってもよい方である。この物語の中にも作家・早瀬勝平として登場し、罹災者の支援に努めている。その描写のもつ独特の訴え方は大空襲をみずから体験した者ならではのものがあり、読者をひきつける。こんなことは2度とあってはならないのである。
(2007/08/11)
福田恵子 『ビルマの花』戦場の父からの手紙
みすず書房、1988
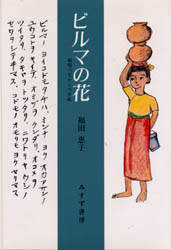
戦場にいる父(秋葉昂氏)と家族との手紙のやりとりが頻繁に続く。しかしある時点から父からの手紙は送られてくることはなくなった。父がいたのはビルマ北部のミイトキーナ、連合軍が中国を支援するルートの要所であった。音信が途絶えたのは、あのいまわしいインパール作戦が中止になった1944年7月以降で、連合軍はミイトキーナへ兵力を投入した時期である。連合軍にとってこの街はビルマ奪還のための第一の攻撃目標であったのだ。
両軍が死力を尽くしたミイトキーナの攻防戦で、この街の陥落は日本軍のビルマ戦線崩壊への第一歩であった。激戦の地でありながら、日本側での記録は少なく、著者の父に関する情報も得られなかったにちがいない。
著者の福田恵子さんは、最初<ビルマ>を、<ミイトキーナ>を、忘れたかったという。どこか深く、トッテモ フカイトコロニ、埋めてしまいたかったと書いている。
この本の全面に父と家族とのあたたかい交流を、現物の手紙の文面で見ることができる。
今でいう絵手紙である。その文面は生活感にあふれるものであったり、幼い子ども達への気遣いが愛情いっぱいに書かれていて涙を誘う。父は工芸科出身なので絵がとてもうまいのである。
ドラマは戦後になって、家族交流の手紙の束を戦場で拾ったという日系2世の米兵カール・米田から手紙が送られて来たことに始まる。著者はやがてこの米兵を次第に父親がわりと感じるようになる。
しかし情報不足の状況からは満たされないものを感じ、父の足跡や行動を少しでも明らかにしたいと感じるようになった。そのため、父の所属した電信隊の機関誌『パゴタ』の会員名簿を入手し、戦友を捜して話を聞き出すことや、戦史資料、戦友会の会報などをむさぼり読むことになる。人の話や資料は貴重だったが、それでもなお、「ビルマの秋葉昴」の姿を視覚的にとらえることはできなかった。
また話を聞いている内に、激戦地でありながら、無事に帰還できた人もいて、なぜ父は帰れなかったのかという疑問が湧いてくる。その事実をさらに追求することに没入していく。本人ですら少し無謀であったのではないかと思えるくらい、その意欲はすさまじいものがあり、胸を打たれる。
この解説を書いている私も2歳の時、父の戦死にあうという類似した境遇なので、この本の、特に絵手紙を見ていると、自然に涙が目にたまり、幼い頃に父を亡くした以降の体験がよみがえってきて辛く悲しい。しかし心温まる物語でもあることもわかった。
亡くなった人の思い出を抱いて生きている人の生き方は様々である。私はこれまで、父の姿を戦場にまで追い求めることは到底できなかった。記憶にない姿を掘り起こそうとすることは、何か恐ろしいものに出会うのではないかとしてむしろ避けてきた。恵子さんとの違いはどこにあるのだろうかと深い感慨に浸ることになった。
ビルマでは花らしいものは見なかったとカール・米田は言う。しかし、恵子さんの父は軍務の合間にビルマの花を何枚も写生して送ってきている。南国ビルマは花が一杯だったのではないか。もう一つは、やさしい気持ちに包まれたカール・米田のさしのべた手によってビルマの地に美しい平和の花が咲いたといってよいと思う。
(2007.08.21、2012.09.10)
金の星社、1977
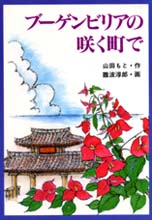
現代・創作児童文学とある。昭和19年の夏、まだ沖縄が焼土と化す前の一時期を力強く生きようとした少年のこころを通して、戦争の悲劇さを子ども達に感じさせる作品である。
松男はブーゲンビリアの咲き誇る遊び場“ビリアの広場”で遊んでいるとき、目をケガしたことがもとで失明してしまう。友達は松男のことを何かと心配してくれるが、松男は障がい者の初期症状のように、しだいに他人の親切さにも反抗的になり、通っていた国民学校にも行かなくなる。場所は沖縄の首里。父は行方不明、母が一人で行商をして幼い松男を育てている。
もし敵が攻めてきたら、兵隊さんと一緒にこの島を守らなくてはならない。でも目が見えない者に何ができるというのだろうか。と自分の不遇さを嘆き、友達とも遊ばず、自宅にこもるようになる。
ばらばら ばらばら さらさら さらさらさら ばらばら…
「ありゃ何の音だ」「あれは久葉の葉が風に鳴る音だがな」と母が言う。松男は久葉の葉音を聞くのが日課のようになった。耳を澄ますと、他にもいろんな音が聞こえる。視覚を失った反面、聴覚が敏感になっていろんな音が耳に入ってくるようになったのである。
がっきがっきと、大きな靴音がふえてきた…こんな町はずれまで、兵隊が入ってきたということだ。(学校へも兵隊が入っているだろうか)(首里城には、兵隊がいっぱいかな)
街の方から、ジャジャジャジャ…と機械の音がひびいてくる。このごろ急に騒々しくなったのは、飛行場や陣地作りが増えたからに違いない。
森の奥か地の底でそうぞうしい音がする。今も自動車が突っ走っていった。軍隊のトラックにちがいない。(おらがのお城を荒らすやつは、だれだ。)松男は心の中でさけんだ。
久葉の葉音は今日もよく聞こえる。松男がいらいらして眠りにつけないとき、母が久葉扇で仰いでくれる。そうすると、涼しくて胸がすーっとする。その体験から松男は久葉扇を作ることに目覚め、力を注ぐことになった。葉を押し伸ばすこと、漂白すること、色づけすることなどである。
やがて戦地からの疎開の話が広まり、労働力にならないものは疎開を強制されることが決まった。松男や友達の家族は北部の国頭に移住することになった。疎開にあたって、作った久葉扇をお墓の中に隠しておいた。疎開先では久葉の葉音はどこにも聞こえなかった。それで取りに帰る決断をする。もはや全島が戦火にさらされ、危険な状態に出くわすことになるのだが。
くばおおぎゃあ(久葉扇は)/いっぺーしださいびーんやー(たいそうすずしいですね)/なー にんじゅんそうれい(もうねむっておくれ)/にんじゅんそーれい(ねむっておくれ)/あちゃー首里はなりてい(あしたは首里をはなれて)/まあんかい とまゆんびーみ(どこへとまるのやら)/くばおおぎぬうかじし(久葉扇のおかげで)/いっぺいしだくないびたん(大変すずしくなりました)… 松男の母が歌い続けた。
(2007.8.27)
集英社、2005
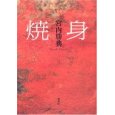
第2次大戦が終わっても、戦争は各地で続いた。しかし近年の戦争は過去のものとその様相を異にしている。近年の戦争は勝ち負けがあいまいである。強大な軍事力を保持していれば、破壊と殺戮はできても結末は勝利するとはいいきれない。争うものが国対国ではなく、相手がテロ集団であるとすると、その存在や所在自体が不明確である。相手側の降伏宣言がないままに泥沼化していく。またそこに参加するものは二者ではなく、国際的広がりを持つ。参加しないと強大国の支配する国際社会から阻害されるのではないかという懸念から強大国を支援する側に立とうとする国が多い。
ベトナム戦争の1963年、ベトナム政府とアメリカの侵攻に抗議するため、一人の仏教僧が焼身自殺を遂げる。このニュースは世界を駆けめぐり、それは崇高な精神の抵抗であるだけに人々を驚かせた。とりわけ欧米社会を驚愕せた。その後、焼身自殺を遂げる人が相次いだ。結果的に南ベトナム政府は崩壊し、アメリカはベトナムから撤退せざるをえなかった。どちらの側にも敗北宣言はないので、勝敗の決着はついていない。
「南ベトナム政府と、圧倒的な軍事力で蹂躙してくるアメリカに抗議するため、ガソリンをかぶってわが身を焼いた。ふるえがきた。誇らしかった。噴き上がる炎が、まったく異なる精神のかたちに見えた。蓮の花のようなアジアの思想が、過激なまでに開花しているのだと思った。」と著者は書いていて、アジアの精神論がまるで次元の違うところから短絡的なものの考え方を否定している。新たな世界観の存在を見せつけた。
著者は当初、僧の名前も彼が焼身した場所さえも知らない。しかし9.11のあざやかな体験から、この過去の事件がよみがえる。どの資料にも名前は書かれていないので、本の中ではX師と呼んでいる。「このおだやかな土地から、わが身を焼くという烈しい思想がどうして生まれたのか」を追い求めようとする意欲がわいてくる。
最初は情報が少ないだけに、著者の過去体験を織り交ぜ、想念が時間と場面を入り混ぜて交錯する。たとえば著者が若い頃体験したバイク事故で、ガソリンをかぶった時の体験がなまなましく描かれている。その体験は体感情報としてX師の焼身の場面を連想させる。
取材の中で、X師の姿はなかなか見えてこない。9.11の事件からは約40年前の事件なので、詳しい情報はなかなか得られない。いらいらするばかりである。
やがてX師はクアン・ドゥック師という名前であることがわかる。しかしすでに伝説上の人物になっているので、どんな人であったかは追求しても答えは容易に返ってこないのである。X師に会ったことのある高僧でも、仏陀の生まれ変わりであるというようなことしか答えてくれない。
全編にアジア的風景と色、香りがただよう。狭い路地、人がひしめき、動いている。汗と揚げ油の匂い、熟し切った果物の香りが漂う街なみ、著者はやがて焼身事件のすべてを演出したといってもいい老僧(ニィエップ師)に出合う。そして事件のあらましを知ることになる。
老僧(ニィエップ師)は「たった一人のアジア人の精神力で、全世界を震えあがらせてやるのが役目だった。植民地支配するフランス、圧倒的な武力でかさにかかってくるアメリカ、そうした欧米の奢りに対して、アジアの意志を見せつけてやりたかった」といいたげである。
自己犠牲は戦争を美化する。反戦デモではなく、宗教的儀礼として、ここでは仏教なので供養としてとらえている。自殺ではなく、焼身供養burning serviceという訳語が定着している。自己犠牲といえば、日本の特攻隊、アラブ人による自爆テロがそれだ。インド独立の立役者ガンジーの非暴力非服従が極めつけである。X師の行動はガンジーの非暴力無抵抗主義に通じるものがある。圧倒的な軍事力に立ち向かう意志のものすごさを際立たせている。しかし、真の独立を獲得するまでにはまだまだ苦闘の歴史と血の海が広がることになるのである。
(2007.9.3)