
フランス・ロレアン軍港で日本への
帰国準備に追われる伊ー29号
sidenkai21.cocot.jp/m422.html
より借用
太平洋戦争開戦後、日本と同盟国であるドイツとの連絡は閉ざされた状態になっていた。それを可能にした唯一といってもよい手段は潜水艦を長駆派遣することであった。しかし日独ともに敗勢にたった時期になるとそれはますます困難で危険な賭のような方法になっていった。潜水艦以外の方法では長距離の移動を可能にする手段がほぼない状態であった。長距離を飛行する飛行機は存在したが、中立条約を結んでいたとはいえソ連上空を飛行することの結果を日本の首脳部は恐れていていた。南方を迂回することは一層の長距離化と飛行条件を悪化させる困難なものであった。
潜水艦の場合でも電波探索の技術が欧米において急速に進歩したため、連絡のための電波を発信することが発信場所を逆探知されて攻撃されること、哨戒・攻撃密度の高い地域では海面に浮上することすらできなかったこと、燃料の補給が難しかったこと、長期に及ぶ艦内拘束のため乗組員に死に至る病人が出ることなどの問題がある。
筆者は日本の潜水艦技術をこの本を読むまで知らなかった。大艦巨砲主義を貫いてきた日本の海軍では潜水艦は地味すぎる存在のため、一般には知られていなかった。しかし日本からインド洋、さらに喜望峰を迂回して大西洋を北上する長距離を航海できる潜水艦を持っていたのは日本だけで、ドイツ側からも大いに期待された。ドイツは航空母艦の設計図のほか、アジアからしか入手できない生ゴム、錫、雲母、タングステン、マニラ麻、コプラなどを日本から供給されることを期待していたのである。一方で日本はドイツの先進的な武器、とりわけ電波兵器技術を導入したくてたまらなかったのである。
いつもながら著者吉村氏の詳細細微に至るノン・フィクション文学には感嘆する。作中に登場する人物は主に海軍軍人達である。その実名がおびただしく登場する。彼らの多くが難局を命をかけて切り抜けようとしている様に感心するが、本サイトは「戦争と庶民」をキーワードとしているので関係ない本なのかも知れない。それで階級や個人名は無視して読み進んでいく。しかし、長時間潜水艦に閉じこめられて、酸素の量は少なくなり、逆に炭酸ガスの量が急激に増してきて乗組員は激しい頭痛におそわれる。それは頭蓋骨のきしむような痛みで、かれらは頭を手でかたくつかんでいたなどという表現が臨場感を誘う。
弱小の遠隔地にある同盟国同士が連絡を取るとき、現在ならどうするのだろうか。通信技術はこの頃よりは日本でも発達しているから、情報のやりとりは問題がないが、兵器類や素材のような物質を遠距離に運搬するにはどうするのだろう。圧倒的な警戒網をくぐり抜けて輸送することは現代でも難しいのではないかと思う。
本著の中でとくに興味をひいたのは伊号第29潜水艦によるチャンドラ・ボースの脱出劇と同艦でドイツに送り込んだ友永技術中佐と庄司元三中佐を日本に送還する際のドイツの潜水艦U234号の話である。チャンドラ・ボースはベルリンで激しい反英放送を行っていたが、突然日本に姿を現したことで内外をあっと驚かせた。その後、自由インド仮政府樹立に邁進するのである。後の方の話はU234で移送の途上、ドイツは無条件降伏をしたことを告げられる。そのためそのドイツ艦に同乗していた日本軍人は技術将校でありながら艦内で自決する。ドイツ人達は自殺の動機を理解できなかったが、日本の武士道精神を賞讃した者もいたという。
文春文庫 1985年

『戦艦武蔵ノート』は『戦艦武蔵』の
取材日記がもとになっている。
雑誌「新潮」に昭和41年9月発表された『戦艦武蔵』の前段階として著者が連載した『戦艦武蔵取材日記』がもとになっている。武蔵はあまりにも巨大で、関係した人間の数も膨大であるため、これを小説にまとめることを著者はためらい苦悩する時期が続いた。「相手はあまりに大きくてつかみどころがないので、取材日記のような形式で、うろうろしながら書いている方が、戦艦武蔵を描けるような気さえしてきた」とも語っている。その経緯と著者が苦悩する姿が詳しく書かれているので読者は深い興味を抱くことができる。そして本著がこの大作家のその後を決定するほどの記念碑的な作品となっていると思う。
吉村氏は「戦争は人間の巨大なエネルギーが根源になっている」ことをしばしば述べている。日本人の大多数は、真剣に生命を捧げてまでこの戦争を勝利にみちびくために行動した。ところが戦後になるとそれをすべて軍部が悪かったとか戦争指導者の傲慢な考え方に導かれていったせいであると言う。日本人だけではない。記録映画を見ると、ドイツ人は、ヒットラーの演説に熱狂しこれを支持していた。新聞も作家も画家も強力に軍に荷担していた。大衆のエネルギーがどのような形を取ったかの究極の事例は特攻隊員の死である。その死さえもいとわなかったエネルギーを直視しなければ、戦争のはかなさ、悲惨さはその姿を鮮明にはしないと著者は述べている。
武蔵という巨艦を生み出す根源は軍部が航空戦の時代の到来を予測できなかった状況判断の誤りだけではなく、大衆のエネルギーを背景にしていることを見過ごしてはならない。このような巨大なエネルギーの蓄積は狂気を生み出すことがありうるのだ。
著者は他人の書いた記述を鵜呑みにして転用するようなことは決してしない。そのため徹底した取材によって事実を確認し疑問を解き明かしている。取材相手の人柄や表情にも注目している。目の付け所は氏独自のものである。著者が異常な関心を寄せたのは、建造中の姿を遠望されることを避けるため、船台をおおったシュロ縄のスダレの存在、最後に沈没するとき、艦は左側に傾き、右側の船腹が露出、その右舷から海に飛び込んだ者は傷を負った者が多かったという話を耳にすると、その原因を聞き逃さない。船底にこびりついた牡蠣によって傷を負ったとのこと、また図面紛失事件と関係した少年のミステリアスなかかわり、など興味深いものがあった。著者が描こうとしたのは、武蔵を媒介とした戦争と人間との関係なのだが、最後に「武蔵」のあまりにも短い命の記録を明らかにしておく。
戦艦武蔵は「大和」とともに、昭和12年度艦艇補充計画の中核であり、翌13年3月29日長崎造船所で起工された。大艦巨砲主義の思想を反映し、国家を安泰に導く不沈艦と考えられていた。昭和18年1月15日に連合艦隊に編入され、同年2月11日には連合艦隊の旗艦となった。その後の戦局の変化、戦術の変貌の前に昭和19年10月24日、フィリピン・レイテ沖シブヤン海において米国艦載機の雷爆撃によりあえなく沈没した。
『伝道者になった真珠湾攻撃隊長−淵田美津雄・心の軌跡−』NHKテレビ番組
淵田美津雄『真珠湾からゴルゴダへ』ともしび社、1954年
この本は現在入手できない。
http://www.being-nagasaki.jp
/genbakutaikenki
/hutidamituo.htm

人はなぜ憎み合うのか、戦争はなぜ起こるのか、それを避けるにはどうすればよいのかという人間の根元的問題に対する解答がここに込められている。
淵田美津雄の名を全国に知らしめたのはあの真珠湾攻撃において大戦果をあげたときである。淵田はこの戦いの第一次攻撃隊隊長で、「トラトラトラ我奇襲に成功せり」と打電したことで英雄になった。彼の書いた未完の自叙伝の中で私の青春はすべて、その一日のためにあったと記している。もちろん昭和16年12月8日のことである。
その後、淵田は海軍の参謀となる。広島に原爆が投下された日の前日まで会議のため広島にいたという。その難を逃れたというよりも必要があって生かされたと言うべきかもしれない。
戦後、淵田は戦犯裁判の証人として、占領軍軍事法廷に喚問されている。これは勝者が敗者を有無を言わさず処刑するという裁判で、法の名を借りた復讐であると感じ、反感と憎悪で胸を焦がしたという。何か反論できる根拠はないかと淵田は日本人捕虜に対するアメリカ側の対応はどうであったかを聞き回った。するとあるキャンプにいた捕虜たちから予想もしない美しい話を聞かされることとなった。
ある捕虜収容所で、一人の若い女性が日本人捕虜に対して献身的な働きをしてくれていた。病人には手厚い看護をしてくれた。一体どうしてあなたはこんなに親切にしてくれるのですかと尋ねると、「実は私の両親が日本の軍隊によって殺されましたから」という答えに唖然とする。この若い女性の両親は宣教師でフィリピンにいたのである。日本軍がフィリピンを占領したので、難を逃れるため、山中に隠れて暮らしていた。アメリカ軍の再上陸によって、ある日、隠れ家が日本軍に知られたため、スパイ容疑で逮捕され、斬殺されてしまったのである。この事実はアメリカに住んでいた娘さんにも知らされた。この女性は日本の軍隊の野蛮さに憎しみと怒りで張り裂ける思いを抱くことになった。しかししばらくしてから父母の教えに学ぼうと決心したのです。ルカの福音書23章34節「父よ、彼等を赦したまえ、その為すところを知らざればなり」が父母の教えだったのです。
淵田はこの話を聞き感動したのだが、それでもまだ充分には理解できないでいた。ある日、所用で行った東京・渋谷駅で一人のアメリカ人がパンフレットを配っていた。それはあのドーリトル爆撃隊の隊員であったJ・デシーザー本人で、彼および仲間の爆撃隊員たちは東京に爆弾を投下した後、中国に不時着したのだが、仲間の何人かは日本軍に処刑されてしまったのである。書かれていたのはJ・デシーザーの入信手記であった。なぜ人間同士がかくも憎しみ合わねばならないのかと考え、人類相互の憎悪を真の兄弟愛に変えるキリストの教えが書かれていた。それを見た淵田は心を開き、聖書を読もうという不思議な欲求にかられたという。その後、淵田とJ・デシーザーは無二の親友となるのである。
憎しみと報復の連鎖を断ち切ることの大切さを知り、アメリカに伝道の旅を行うことになる。どの教会でも多くの人々に感銘を与えることができた。さらにあのハワイでも伝道集会を何度も行っている。淵田は自分が真珠湾の攻撃隊長として多数のアメリカ兵を死傷させたことを決して謝罪しなかったそうである。このことは武人としての信念に基づくものでこれまた感心させられる。
この話はどうすれば戦争や紛争を無くすことができるかという最大の問題に対する解答を提示している。
キリスト教の敬虔な信者になればよいのだろうか。あのブッシュ大統領は敬虔なキリスト教信者だと自他共に認めるところであるらしいが、報復の連鎖であるイラク戦争を開始し、いまだ終結する見通しはまるでない。ブッシュが大統領でいる限りいつまでも戦争は終わらないと嘆いているアメリカ国民の声をテレビで聞いた。
この問題解決の糸口をどのように実現していくのか、人類に対する大きな課題である。
新潮文庫、1973年

連合艦隊司令長官
山本五十六
私は暗号技術について調べているとき、たまたまこの本の中に戦時における暗号に関する詳しい記述があるという紹介文を見た。開戦直前における日米交渉で、ハルは日本大使が持ってきた最後通告の内容をあらかじめ暗号解読により知っていたことが、後に明らかにされている。さらに山本長官が前線を激励のため訪問するとき、暗号解読による待ち伏せ攻撃にあう。ブーゲンビル島上空において戦死されたときの状況については、暗号解読がらみで多様な推論を著者が行っているところは圧巻である。さらに搭乗機を撃墜したのは誰かという問題でも結論は単純に決めがたいなど興味を引かれる内容である。
当然それ以外のところにも目を向けることになった。なにしろ山本五十六といえば太平洋戦争における日本最大の英雄であり、聖将とも言われていた。日本の全国民といってよいほどの多数から崇拝されていたし、外国からも注目されていた人物である。昭和18年6月5日、元帥山本五十六の国葬が行われた。伝記物として書かれた本もかなりの数に及ぶ。その中でも本著は第一級の作品であると紹介されている。
私はこの小説を詳しく読んだのは2回ある。一回目、読んでみると、少年時代に抱いていた偶像が壊れていくのを感じた。妻と子供4人がいるのだけれど家族に対する記述はほとんどなくて、新橋の芸者との話や博打が何よりも好きという記述が随所に出てくるのには閉口したからである。遊びが遊びの限界を越えている。人物の判断に花柳界での遊び方や博打好きかどうかを基準にしていたらしい。外国勤務、艦隊勤務の長い海軍の軍人とはこういうものだという解説記事も見たのだが家族とは疎遠であったのか、著者があえてこのような記述法によって人物像を浮き立たせるようにしたのかは分からない。
二回目、読んでみると、その中に女性との関係や博打好きであることを含めて山本の赤裸々な人間像を描いているが、なるほどいろんな階層の人たちから親しまれ、敬愛された人物像であることがよく分かった。
ロンドンの軍縮条約の時の交渉経過が、詳しく述べられていている。2・26事件の時の海軍の対応の仕方、日独伊三国同盟や対英米戦争に反対しながら、連合艦隊司令長官に任命されてから、真珠湾奇襲の構想を固め、ついに戦争開始の引き金を引かざるを得なかった苦渋の選択に胸打たれるものがある。
岩波ジュニア新書 1998年
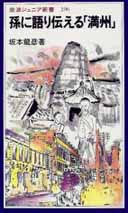
飯山達雄 『小さな引き揚げ者』
草土文化社、1985
書名で明らかだが、これは著者が孫に語り伝えるために書かれた満州である。いまでは地図上に見ることのできない満州で、日本人はいったいどんな体験をしたのだろうか。自国の歴史の暗くて陰惨な事実を書き記すことには抵抗があるし勇気もいる。著者は身体に刻まれた歴史を孫に伝えるというスタイルで語っている。それは満州での体験、友人の死、残留孤児、731部隊におよぶ。
著者の家族の場合、著者の父が1942年、単身で満州に渡り、千振開拓農学校の教員となり、その後著者ら家族5人で移住を果たしている。「満州に行けば大地主になれる」という宣伝文句を信じ、夢と希望を抱いて移住した日本人は150万人に及ぶ。そのほとんどが悲惨な目に遭い、命からがら帰国することになるのである。その間、広野の新天地に血を沸かせたものの期待は次々と裏切られていく。
移住した土地はそこで農耕をしていた中国人から安く買いたたいた(奪った)土地であり、そのため定住地を追われた原住民の怒りを買い、撤退するときには逆に襲撃されたりしている。小作料をとって原住民を働かせていた土地も多い。
匪賊に襲撃されることも、年間2万6千回におよんだ年もある。そのため軍隊と同じで銃を持って戦わねばならなかった。農民として移住したつもりが兵隊と同じことをしなければ生きていけなかった。戦死した者も多数に及んでいる。しかし開拓団員は兵隊と同じ待遇を受けていないと不満を漏らしていたという。
この本の最初の部分には満州の歴史が書かれている。満州族のこと、英国の仕掛けたアヘン戦争以後のこと、帝政ロシアの南下政策を背景にしたロシア軍によるブラゴベの大虐殺のような悲惨な事件や反日抗争の土竜山事件などが起こっている。この地域は日本だけでなく列強に狙われていたのである。時代背景は農民にとって安全と豊かさを約束してくれるものではなかった。
しかし早くから移住した開拓民にとって、それは短い期間であったが豊かな時期もあった。その豊かさは満人の安い労働力に支えられていたともいえる。しかし終戦の年の8月9日、日ソ中立条約を破ってソ連軍が国境を越えて侵攻してくるのである。それに対していち早く、守ってくれるべき関東軍は逃げてしまった。しかも橋を破壊していった。侵入してきたソ連兵はドイツで近代戦を戦ってきたどう猛な部隊で、開拓民は武力の格差に圧倒されて退却するしかない。これらのソ連兵に蹂躙されるか、それをおそれて集団自決した村も多数あった。頼みとする日本軍は真っ先に逃げてしまった。そのとき開拓民のために用意されていた列車に軍の家族だけを乗せて逃亡したという。
さらに著者らはソ連軍の労働力として働かされた。シベリヤに送られた者もあった。開拓民は徒歩でハルビンなどの都市に向かったが、これは生き地獄とも言える逃避行であった。このとき幼少の子供を連れて帰ることができず、現地に残してきたことが、中国残留孤児の問題として後々にその陰を残している。このような悲惨な状態に対しする国の対応は実にお粗末で、棄民として見捨てる態度に終始したため、満州からの引き揚げは遅れに遅れた。その原因には大本営参謀、浅枝繁春大佐の超楽観的な報告書の存在があったことが知られている。難民の状態は寒さに向かう中で悪化し、各地の収容所は死体収容所になっていった。
写真家・飯山達雄氏は日本政府の無策に怒って旧満州に潜入し、難民の惨状を写真に撮って帰国、GHQに引き揚げを訴えた。同氏の献身的な努力により1946年8月20日から引き揚げが開始された。
さらに731石井部隊のペストノミ爆弾、細菌戦、についても本著で詳しく記述されている。戦後になって米軍も石井式細菌兵器と似た方式が使われ、それに必要なネズミの飼育が日本で行われていたという記述には驚かされる。
語り継がなければならないのは満州の崩壊は何を物語っているかということである。
関東軍による民間人置き去り事件について、著者は朝鮮人、中国人などの民衆を踏みにじった日本の軍隊は、日本の民衆をも踏みにじっていたことが満州の敗戦史には浮かび上がってくると述べている。
十月書房 1983年
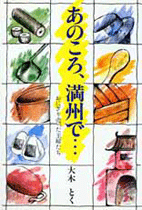
兵士が出征するとき、涙を流した人は帰って来られないというジンクスめいた話を聞いたことがある。悲観的なことをイメージする人はその通りになるともいう。女性の場合はどうであろうか。どういう人が帰還できるのだろうか。著者は陸軍将校のご主人の満州勤務にともなって旧満州熱河省承徳で平穏無事な生活をしている。
信じられないことであるが、昭和20年日本が終戦を間近にしている時点で日本のおかれている状況を何ら把握できていない。そのため突然、疎開退却を指令されてあわてて着の身、着のままの脱出行の準備をする。将校の家庭でも新聞にも放送にも接していないのは驚きである。たぶん満州ではB29による日本本土空襲のようなことも少なかったので日本が敗勢にあることを実感できなかったのではないだろうか。敗戦の日以降は一転して現地の中国人に襲われ身の危険にさらされることになった。中国人だけでなく、どう猛な囚人部隊のソ連兵に日本人が蹂躙されるのを目の当たりに見るに付け、将校の夫人たちは先ず子ども達を殺して自分も死ぬという自決のことしか念頭にない。
ところが著者は死ぬのはいつでも死ねる。どうぞ死にたい方はお先へと言う。あなたのその着物や布団は私がいただくわとさえ言う。海の上をはってでも日本に帰る決意を固めている。この事態においてその決意は生きる知恵を生み出すのであろう。でもどうやってと疑問を投げかけられたとき、まず寒冷地では必需品の毛布を売ってお金を作り、お米を炊いておにぎりを街頭で売りましょうと提案する。ところが並の人は高価な毛布を売りに行っても中国人に奪い取られてしまう中で、著者は毛布を握りしめ必死の思いで売ることに成功する。おにぎりを作るにも鍋や竈からマッチ一本、箸一本に到るまで何一つ所持していない。それらを強引に隣家の中国人から借り受ける。商売の糸口をやっとの思いで掴んだことになる。
この本は著者の体験記であり、崩壊する満州国の最後を生活者の側から描いたものとして貴重なものである。しかし、この本は単に終戦時の悲惨な体験記にとどまらない。その時の状況にあった生き方の本であり、今でいえば、ビジネスの成功物語と見ることもできる。第1部おにぎりありがとう、中国・奉天路上おにぎり屋、第2部は“幸せ”求めて、渋谷、道玄坂ファッション店 からなる。奉天路上のおにぎり屋で命をつないだのであるが、あまりの多忙さの中で、三男を失っている。しかし著者の家族は夫妻と子供3人と共に無事に帰国をはたした。その状況は胸打たれるものがある。車窓から焼け野が原の日本の都市を目にしているはずであるが、故郷の森や民家は十何年前と少しも変わっていない姿を残していたと書かれている。
ところで奉天に集結した日本人難民はどうしてそのまま日本に帰国できなかったのか、なぜ路上で販売生活をしなくてはならなかったのかを疑問に思われる方は前掲の坂本龍彦『孫に伝える満州』をご覧ください。著者の場合は将校の家族だけに、満蒙開拓団の人々のように国から見捨てられるほどの悲惨さを味わったのではないと思う。
やがて著者らは東京・渋谷で商売を始めるのだが、著者は時代の流れを瞬時に見通す才覚に恵まれている。赤貧の時代には食べ物屋、それを真似する人が多くなるとローソク屋、薬屋、ソ連兵を使った石炭の仕入れなどと売り物を変えていく。どの仕事も多忙をきわめる。帰国後は貝類の販売、古着屋から呉服屋、時代の流れを先読みして洋装店へと姿を変え、いずれも成功させている。旧軍人仲間が慣れないやり方で商売をするのを手伝っている。家族への配慮をするゆとりは全くないが、旧軍人仲間や親戚の人たちのの面倒をよく見ている。たくましい生命力を持ちまた大変な努力家であることが分かる。
「戦争とは、世の中の文明も、文化も、人間の誇りも、義理も人情も、いっさいを無にするもの。このうえもなく馬鹿らしいものであることを分かって頂ければ幸いです。」で結ばれている。
岩波新書 1986年
著者は昭和6年(1931)生まれである。これは満州事変の勃発した年である。日本はここから延々15年も戦争をし続けた。15年戦争といわれるゆえんである。
著者は子供の側から見たあらゆる史実のうち、特に教育史に関係のある部分を集大成した。それがシリーズ『ボクラ小国民』で、氏のライフワーク的業績である。本著はこれを背景として、戦時下の子どもの風景を編年体形式でまとめたものであると、「まえがき」に記されている。
太平洋戦争のことをだいたい知っているつもりでも、山中氏の著作を見るとまだまだ浅い認識であることに気づく。例を挙げてみよう。
集団疎開で農村に疎開した学童が上級学校の入学考査期日にあわせて、決められた期間に帰京する。運悪く、東京大空襲に遭遇して死亡したり、戦災孤児となってしまうことがあった。疎開地の学寮の教師が空襲で死亡した学童の名前を発表すると、寮生の間から歓声が上がったり、口々に「いい気味だ」というのを聞いて慄然としたとある。友人の死を悼むどころかその逆であったことは、いかに疎開地での人間関係が荒廃していたかを物語っている。食料品の輸送が途絶えたまま、集団疎開は一、二年生にまでおよんだ。それは子どもの生き残りが目的でもあるが、空いた校舎を本土防衛軍の施設に転用することが目的だったことも書かれている。
尋常小学校が国民学校にかわると、「体錬科(いまの体育)」が強化され、「正常歩」という歩き方、行進の仕方が国民学校生にはいたるところでつきまとった。それは寒さの厳しい時期には過酷なものであった。そのつらさを口にしようものなら、「満蒙や北支の兵隊さんのことを思え」、「天皇陛下のおんため」という答えが返ってきた。それでも小国民の男子はお国のために陸海軍の士官になることを夢見ていた。女子も軍隊のような教育に耐えていた。
同世代の者には奉安殿、少年団、八紘一宇、勅語、一億一心、前へならえ、鬼畜米英、空襲警報、神社参拝、買い出し、紙芝居、欲しがりません勝つまでは などの言葉を忘れることができない。いちばん切実なのは食料が次第に身辺から消えていったことだ。戦争をすると空腹に耐えねばならないのだ。
最終の節で、戦後教育とその後の動向についても触れている。筆者は「戦中戦後の教育というのは、天皇の奴隷になるための教育だったのである。そんな教育が良かったとか、そんな教育へ戻したいというのは、明らかに歴史に逆行する愚行でしかない」と述べている。
2005年8月29日放送

広島県産業奨励館をセットで再現
(原爆ドーム 破壊前)
これはTBSが「涙そうそうプロジェクト」と称して、視聴者より涙がとまらない体験を募集し、その応募作の中からテレビドラマ化したものである。
本サイトでは「戦争と庶民」をキーワードとした感動的な小説ほかを紹介している。戦争体験のまったくない平和な時代に育った人々に訴えるにはどうすればよいのだろうか?小説のような文字ではなく、テレビドラマとして映像で訴えることは優れた訴求力をもっていることがわかる。心に残る作品である。
最初の場面は一人の老人(西田敏行)が修学旅行の生徒たちを相手に60年前の夏の日の話をしている。場所は広島の平和記念公園、被爆前のこの地は落ち着いた街で民家や商店が建ち並んでいた。庶民の平和な暮らしが営まれていた。そこに両親を亡くした4人の姉弟が助け合って暮らしていた。
このドラマは原爆投下までの20日を取り上げている。アメリカの為政者たちは原爆投下の決断を下し、その場所を広島と決め淡々と実行に移していく。もうすぐ平和な生活は消滅してしまうのだが、庶民はそれをつゆ知らず、懸命に生きている。原爆を搭載したエノラゲイとして知られている悪魔の飛行機が飛び立ち、刻々と広島に近づく描き方に感心する。アメリカ側の悪魔の動きと広島での姉妹の恋愛物語や軍部へのささやかな抵抗物語などが少しずつ同時進行する。やがて来る運命の瞬間を知っているものにはいたたまれぬ感情を引き出すことに成功している。
このドラマを情感深いものに仕上げているのは、出演者の熱演にもよるが、原爆ドーム(広島県産業奨励館)や街並みをセットで巧みに復元したためであろう。
平和公園に灯された火は、世界中から核兵器がなくなったら消されるという。その日が来ることを願ってやまない。
キャスト:
長女 志のぶ(松 たか子)
二女 信子(加藤あい)
三女 真希(長沢まゆみ)
長男 年明(富浦智嗣、後の語りべ:西田敏行)
脚本:遊川和彦
主題歌:涙そうそう 夏川りみ
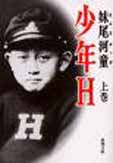
この小説は著者の戦争体験を少年時代の舞台である神戸を背景にして描いたものである。全編が多数の小話からなっているが、どの小話もわかりやすくて面白い。そのためか出版と同時にベストセラーとなった。
私は妹尾氏よりは年少であるが、国民学校に通い、戦時の体験をしたものとして、古い古い感覚が戻るのを感じた。たとえば「焼け跡の熱気から生まれるのか、つむじ風が時々吹き、いままで嗅いだことのないムッとした焦げ臭い匂いが町を被っていた。」という記述に当時をはるかに思い出した。「家の中がすごく明るかった。電灯に被せてあった灯火管制用の黒布がはずしてあったからだ。」では終戦になった直後の我が家もそうだったことを思い出した。
しかし、山中恒氏がこの小説に猛反撃を加えている。山中恒、山中典子『間違いだらけの少年H』(勁草書房)では『少年H』は時制がでたらめで史実が間違いだらけであるという指摘である。これはまるで裁判記録のような内容の本である。
私は幼少年時代の記憶は夢の世界のようなものだと思う。一般に幼少年時、記憶に残っていることは決して忘れないほど鮮烈なものである。しかし時間の観念があいまいなので、時制が逆転していたりする。まさに夢の中の状態である。
ところで妹尾河童氏が描いた絵は、誰も真似のできない細密画のような線画が特徴である。同氏が文章を書くとどうなるのかを期待して読んだ人も多いと思う。精細に描くために歴史年表や過去の新聞に目を通すことによって記憶のあいまいな点を補足したものと思う。史実の記述誤謬は許されるべきではないが、私はあいまいさを許容した方が夢の中の世界のようで話を面白くする効果がでてくると思う。
山中氏の指摘の中に長楽国民学校の二宮金次郎の銅像を撤去の日、友人林と海岸を歩くシーンがある。林は近く神戸学童相撲選手権大会に出場するのだが、海岸では遠くに入道雲が立ちあがっているのを見る。山中氏はこの時期は三学期(真冬)で、この時期に入道雲が立つはずがないとこんな所にも非難を浴びせかけているのだけれど、真冬だと断定するにはこの小学校の銅像撤去の日が明らかにならなくてはならない。根拠が明確ではない。相撲大会を真冬にやりますかね。またこんなことに難癖をつける必要があるのだろうか。少年Hは入道雲に憧れている。好きなのだ。戦時の緊迫した状況下のムシャクシャした気持ちをかき消すために、少年たちの海には入道雲が立ち上がり、それが夢や希望を象徴しているのだと思う。
もう一つ、父・盛夫との関係であるが、少年Hは父との会話を大切にしている。「これは絶対に他の人にいうたらあかんよ」とか「これは二人の秘密にしとかなあかんで」という会話がかなり出てくる。父・盛夫は実は少年Hが戦後何十年も経過した後での妹尾氏そのものなのだと見た方がよい。戦時にすでに天皇の戦争責任を語る少年がいたはずはない。著者がそれを否定しようと、少年H自身も戦後何十年を経た後のH氏が過去を書いているのである。『間違いだらけ…』には何とすごい一家がいたものだと皮肉たっぷりに書いているが、その非難は当たらないと思う。父と子が実質同一人物なので秘密の二人だけの会話がしばしば交わされるのである。小説と記録とは遠い記憶をもとにして書く場合には大いに異なる。記録と記憶は違うものである。それを承知で読めば読者は納得できる。
『少年H』の圧巻は下巻の実弾射撃、蛸壺、空襲、焼け跡、機銃掃射、捕虜などである。上巻のオトコ姉ちゃん、海の子も面白い。
もはや少年ではなくて、銃後の守りについて一家の支えている姿は立派な大人の姿に思える。戦時下の少年は実にたくましかったのだ。