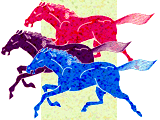
『乗馬の記憶』 (その1)
ーわが青春暗黒記ー
エッセイ 1-1
金城学院大学 元教授
社会学
横浜市
私が自分でも思いがけず乗馬と縁ができたのは、1 9 5 6 (昭和31)年の秋であった。そのころ大阪市の近郊にある箕面村(現・箕面市)に住んでいた私は、近くの大阪大学文学部哲学科の学生として社会学を専攻していた。
もう4年目に入っていて、同級生たちは卒業を間近にして卒業論文に集中しており、また就職もほぼ決まっていた。それなのに私は、卒論にも就職活動にもかかわらず何もしていなかった。もう自分自身を見棄てていたのだ。
その原因は健康問題だった。
高校時代までいたって健康だった私は、中学時代の少年野球チームから高校時代の軟式野球部まで、戦後間もないあの時代の典型的な野球少年として活動していた。その延長線上で、大学入学後は当時近畿大学リーグ1部に属していて甲子園球場を舞台として公式戦を戦っていた阪大硬式野球部に入り、新入生ながら控えの二塁手として時々試合にも出ていた。
ところが私の不注意で、その野球が仇となり、すっかり健康を害してしまい、春季シーズン終了とともに引退せざるをえなくなった。それから私の体調はきわめて不安定となり、ちょっとしたことで微熱が出たり、倦怠感を覚えたり、味覚がなくなったりして、不安感から勉学意欲もどんどん失せていった。それでも止むを得ず大学の授業には顔を出し、あるいは出さなくても他人のノートで試験だけ受けて、講義科目の単位は3年目までで全部取得していた。それで、4年目は卒業論文だけが残っていたのだが、私にはとても卒論に挑戦する気力がなかった。
その夏にはまたしても微熱が出て、エアコンなどなかった当時の自宅内の暑さは身体に堪えた。そこで窮余の一策として、そのころちょっと知り合いだった人が村内で営んでいた農園に住み込ませてもらって、逆療法のような形で遊び半分の農作業に従事することとなった。この知人はもともと東京の富裕層で、戦時中この村に疎開してきて山麓に大きな土地を買い、住居として西部劇に出てくるような木造のコテージを建てて住み、田圃と畑を耕作していた。
ところが数年前にその人は東京へ戻り、銀座に有名な洋品店を出店してその経営に専念し、農園は農業高校出の若者たちを雇って任せていたのだ。そこで私は、彼らに教えてもらいながら田圃の草刈りや牛の飼育を手伝った。夏の炎天下の草刈りは、箕面山から吹き下ろす風のせいでとても爽快で、自宅で感じる暑苦しさとは無縁であった。こうして私の目論見は的中し、2ヵ月ばかりの農園暮らしのおかげで炎暑から逃れることができて秋を迎え、家に戻った。
ところが、まったく頭を使わずそれなりに快適だったこの2ヵ月間の生活は、私からものを考える習慣を失わせたらしく、また炎暑が去っても身体の倦怠感が去らなかったこともあって、復学して1年遅れの卒論の準備をする意欲がどうしても沸いてこないのだった。
こうして戸惑いながら私がたどり着いた結論は、やや突飛だが、退学して下関か北九州で漁船に乗り組んで、雑用係にでも使ってもらうことだった。なぜ西日本の漁船乗組みなのか。当時、韓国が強引にいわゆる李承晩ラインを設けて、公海上であってもそのラインを越えて操業する日本の漁船を銃撃して拿捕するという事件が多発していた。死傷者や逮捕者もかなり発生しているようだった。このような状況では、おそらく下働きの漁船員に応募する若者は減り、私のような漁業労働無縁の未熟者でも雑用係のような仕事なら雇ってもらえるのではないか、と思ったのである。
普段の生活では体調不安定ゆえにシャキッとした生活ができない私でも、命懸けの仕事となると緊張感で引き締まった生活ができるのではないかという、今から考えるとかなり甘い算段であった。もう一つ考えたのは、漁船に乗り組めた場合にはいつ死ぬかわからないので、それまでにしたいことをしておく、ということである。
では、そのころの私のしたいことは何だったのか。それが乗馬だった。私は高校2年生のころから、やや晩成であるが映画が好きになっていた。主に見たのは戦前のフランス映画やドイツ映画(というよりオーストリア映画)だったが、アメリカ映画でも西部劇だけは例外的に好きだった。中でも、ガンマンが酒場や町中でガンファイトする決闘物より、雄大な草原や砂漠を舞台にした騎兵隊物が好きだった。
戦前では『駅馬車』、戦後では騎兵隊3部作の『黄色いリボン』『アパッチ砦』『リオ・グランデの砦』など、ジョン・フォード監督の作品で騎兵隊が颯爽と馬を乗りこなして疾駆する姿に憧れたのである。この私のいささか子供っぽい嗜好には、もう一つの要因が影響していた。医師であった私の叔父が戦時中軍医として招集され北支戦線に従軍したとき、スポーツ万能・馬術堪能・冒険好きの彼が、当時の陸軍で残り少なくなっていた騎兵隊の奇襲作戦に参加して敵陣に切り込んだ、という話を聞いていたのだ(両軍とも装備が劣悪だった北支戦線では、いまだに西部劇のような戦闘もあったようだ)。
このような事情で、私はいつか乗馬を習いたいと思っていた。 そこで私が立てた計画は、家出してひとまず神戸に行き、そこで1年間ぐらい働きながら乗馬クラブ(神戸には心当たりのクラブがあった)で思う存分馬に乗り、そののち下関か北九州の漁港に赴く、というものだった。思い立ったらすぐに実行というわけで、10月初めごろに私は家出を敢行した。
そのとき、家からウィスキーを5~6本持ち出した。私の父は金儲けとは縁がなかったが貰い物が多い職業だったので、貰い物のウィスキーが溜まっていたのだ。神戸に着いてから働くにしても、少しは軍資金が必要だった。私はその足で大阪の繁華街・梅田の飲み屋街に行き、開店準備中のバーを訪ねて、バーテン相手にウィスキーを売り込んで幾ばくかの現金をせしめたのち、神戸に行った。
神戸に着いてから、私は当時下町の繁華街であった湊川近くの新開地に赴いた。そこの安宿で2~3泊しながら少し遊んだ(酒?女?)のち、近くで超安値の下宿屋を見つけ、また三宮で働き口も見つけた。下宿は低湿地にある狭いボロ家のI階建てで、家主の老夫婦が暮らしている居間の隣の1間が貸間だった。その狭い貸間はカーテンで2つに仕切られ、片方に私の先住人が住んでいた。先住人はかなり年配の男性で、神戸新聞社の広告局で広告デザイナーをしているという独り者だった。私は夜の仕事に就いたので、無口そうなこの人とはいつもすれ違いで話をしたこともなかった。
ずっとのちに、戦後を代表する小説家の松本清張が印刷屋の版下小僧から朝日新聞西部本社広告局の広告デザイナーに登用されながら、不遇をかこった過去があったことを知ったとき、私はこのときの彼を思い出した。そういえば、こののち1年半たってからもとの学生生活に戻って無事大学を卒業した私は広告会社・電通の大阪支社に勤めることになったのだから、私はこの人と因縁があったといえる。
私が見つけた三宮の仕事は、阪急電鉄・三宮駅出口にあるアルサロのボーイだった。アルサロとは、今はないが当時流行っていた「アルバイト・サロン」の略称である。これは、昼間堅気の職業に就いている素人の女性が夜だけアルバイトとして女給を務める酒場、を意味したものだった。素人女性による接客という物珍しさと、高級バーやキャバレーなどに比して割安な料金が魅力になって、客を集めていた。
私が勤めた店は、駅の改札口を出たところにある地の利のおかげで、結構繁盛していた。2階建ての店で、アルバイト女給が7~8名出勤しており、お客が25名程度で4人掛けのボックス席が満席になった。女給は洋装だったが、ママさんは和服姿で出勤していた。ほかに男性スタッフが、ボーイ長1名、バーテンダー2名、ボーイ1名の計4名おり、最も下っ端のスタッフである“ボーイ”が私だった。
この店の経営者は赤ら顔で大兵肥満の初老間近かの中年男で、客が立て混んでこない夕方などに時々店に立ち寄った。ママさんは中年に差しかかったちょっと権高な感じの体格のよい割合綺麗な人で、経営者に囲われていた。彼は店が暇なときボックス席に女給たちを集めて、「ママさんも世が世ならここにいる人ではないのだが」などと喋っていた。私はそれを聞いて、もし本当なら彼女は戦争の余波で没落した富裕層の子女だったのか、などと想像した。
女給たちは、何しろアルサロなのだから余り派手な衣装は身につけず素人っぽく装っていたが、本当のアルバイトは少なく、たいていは女給を本業とする連中だった。その中で、純粋アルバイトの姉妹2人組がいた。しかも彼女らは、何と神戸市役所の高卒職員だった。彼女らのアルバイト目的ははっきりしていて、両親を助けて家を建てることだった。この件にも私は想像を巡らせ、彼女らの自宅はひょっとすると戦災で焼け落ちたのだろうかと思った。
まったくの堅気の彼女らはセミプロの女給たちと多少肌合いがちがったが、結構美形で馴染み客もついていて稼ぎはよく、着々と自宅建設資金が溜まっているようだつた。店は夜11時半の終電間際に閉店となるのだが、女給たちの中にはそのあと飲みに行ったりする者もいたが、この姉妹は必ず終電で自宅に帰って行った。彼女らは自分たちのアルバイト目的を公言していたし、堂々と堅気風を吹かせていたが、仲間の女給たちはそれに反発するでもなく、みんな仲良く働いていた。
私は閉店後国電(現・JR)に乗って三宮駅から西へ2~3駅先の湊川駅まで帰るのだが、同方面に帰るボーイ長や女給たちと一緒に湊川の飲み屋街で飲んで帰ることもあった。セミプロの彼女たちもあまり水商売の垢が身についていないようで、違和感を感じずに付き合うことができた。
ボーイとしての私の仕事は、午後3時ごろ店に顔を出して開店準備の雑用をこなし、5時の開店と同時に白い制服を着て店のドアの前に立って呼び込みを行い、店内に客が立て混んでくると呼び込みを止めて店内で酒や摘まみを運ぶことだった。開店準備作業の中に、ビールの在庫が少なくなって緊急のビール運びが発生することがあった。そんなときは、ボーイ長と一緒に近くの酒屋からビール瓶を運ぶのだが、左右の指の間に瓶の首のところを挟んで、1人が片手に4本づつの計8本、2人で計16本を運び込んでー息つくのだった。
店内で酒類を客席に運んで行くと、お客から酒を振る舞われることがあった。私はのちにアルコール大好き人間になるのだが、当時はまだ強くなかったので、飲みすぎた私の様子を見ていたバーテンから「ボーイさん、飲みすぎると動作が鈍くなるね亅などと注意されることがあった。しかし店の人たちは、学生上がりの急造ボーイに優しく接してくれ、仕事を辛いと思ったことはなかった。
11時半ごろに閉店になると、ボーイ長と私にはその日の最後の仕事が待っていた。それは、生ゴミではない水溶性のゴミ(女性用トイレの廃棄生理用品をふくむ)を近くの下水道開口部へ棄てに行くことだった。私はその行為が合法なのか違法なのかわからなかったが、ボーイ長に訊ねても仕方がないと思い、彼に従って毎晩投げ棄てていた。
ボーイ長は、色白の小柄な35歳前接の気のよさそうな、あるいは気の弱そうな、男だった。彼は旧制・滝川中学の出身だったが、彼の在学中その野球部がのちにプロ野球の名選手となる別所投手、青田外野手らを擁して甲子園で大活躍した。彼は別所と同級生だと言っていた。日米開戦のころ彼らは卒業し、別所はプロ野球の南海軍(戦後は南海ホークス)に人り、彼は船のボーイ(瀬戸内海航路?)になった。彼は母子家庭に育ち、上級学校への進学は望めない境遇だったから、どうせなら中学校ではなく商業学校に行きたかったのに、母親の見栄で中学校に進学させられて損をした、と言っていた。
当時中等教育経験者(旧制の中学校、商業学校、工業学校などの卒業生)の比率は17%程度で、高等教育経験者(旧制の大学・高校・高専・高師・陸士・海兵などの卒業生)は5%にも達していなかったから、商業学校の卒業生は企業などで即戦力として期待され、実学を学んでいない中学校の卒業生よりも就職状況がよかったのだ。敗戦で職を失なった彼は夜の世界に入るのだが、そこで素敵な女性に出会って結婚した。その女性はホステスだったが、三宮で有名な姐御肌の美人で、彼の結婚生活は幸せだったようだ。ところが彼女が病気で急逝し、彼は独身に戻って母親と2人で淋しく暮らしているとのことだった。
2人いるバーテンのうちの1人は、ボーイ長と同じぐらいの歳で、気立ても手際もよい渋い感じの“しっかり者”だった。もう一人のバーテンは、20代半ばのハンサム・ボーイだったが、経験年数が少ないためか、少し仕事にムラがあるようだった。このハンサムは、当時野球で有名だった浪商の出身で在学中はサッカー選手だったようだが、たしかにスポーツマンらしいキビキビ感があった。大学(浪商の系列校・大阪体育大学?)に進学したが、1年で退学したとのことだった。ボーイ長の月給は1万5千円ぐらいで、生活は苦しいと言っていた。
当時の1部上場企業の大卒初任給は7千円~1万円ぐらいだったから、母親を養いながら再婚を狙っていた彼の身になればもう少し欲しかったことだろう。バーテンたちは調理技能があるだけに、形式上は男性スタッフ全員を率いる立場のボーイ長よりも、月給は高かったかも知れない。私自身の月給がいくらだったのか、迂闊にも思い出せないのだが、たぶん5~6千円ぐらいだったと思う。
このようなアルサロ・ボーイ生活がスタートすると同時に、私はお目当ての乗馬クラブに入会した。
(その2(次回)につづく)ーーーーーーーー
ご感想ご意見などありましたら『勢陽』の掲示板にお書きください。