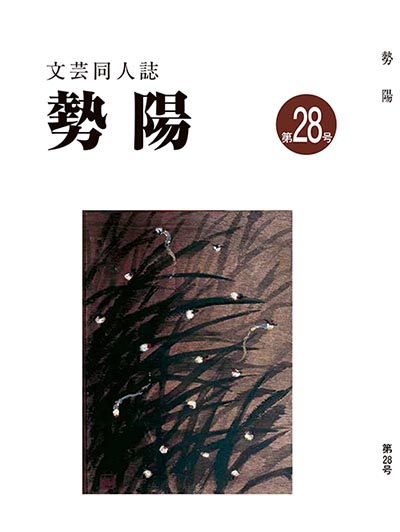
小説
『愚直の果て(後編)』
P134-163
バスで家に帰り着くと祖母がカンカン照りの太陽の下、庭で糸を引っ張って機の糸を筬に通す作業をやっていた。
子供のときから今迄にこんなこと見たことなかったのに、と思ったが「只今帰って来たよ」というのに「おゝ
そうか」と言って又仕事に戻った。「祖父はどうね」と言ったが「新屋に寝とる」と言う。
我が家と言っても母屋は大きな麦稈葺きであり、おまけに納屋と言はれる作業場も麦稈葺きであった。
祖父が大工としての腕のみせ処がなかったのは何と言っても父の怪我による身障者になってしまった為であったと言はねばならない。只一つ小さな離れ座敷の瓦葺屋根を建てただけであった父は戦傷者ではなかった。
この離れの新屋に寝とると言う祖父の処に行った。「爺やん帰って来たよ」と言ったが目を見開いて口を動かしているだけで何を言っているかわからなかった。
これは大変なことだ敗戦のどさくさで充分に医者にもかかれずに死んでしまうのかと思った。
「婆やん弟はまだ帰って来んのか」というとまだ夏休みが終っとらんので毎日学校に行っとる。
これはおかしな話であるが戦争中はどこの学校も夏冬休みなしでやって来てそれが続いているのかと思った。「それでは学校を見に行って来る」と言って私は自転車に乗って出かけた。
前には宮川が流れ後は山が迫っている内城田国民学校であった。運動場の上には神宮山蓮華寺という鎌倉時代からのものと言はれる本堂や山門観音堂五輪塔がある、内城田村は山村であり何処にも爆弾は落ちなかったから無事であるのだろうか。
十分程で学校についた。学校の前の運動場に来て吃驚した。
- 134 -