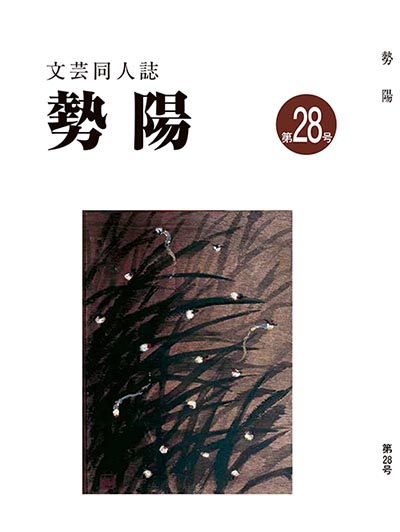
小説『大豆の花』
P 1-27
「きれい」
おもわず声を上げて、縦四十センチ横三十センチ四方の木で作られた麹蓋とよばれる箱のなかの発酵した大豆
に咲いた黄色い花にそっと手を触れた。花の胞子がふわふわ飛んだ。指の先にも黄色い胞子が粉状になってついている。
「この大豆も半年後には艶のある味噌になるんや」
多恵の母は、大甕に発酵をさせた大豆、塩、麹、水を入れて毎日一回大きな木杓文字でかき混ぜる。半年もたつと艶のある味噌が出来てくる。多恵は台所の隅に置いてある味噌の入った大甕を頭に浮かべた。
「私も艶のある味噌になってやる」
多恵はそんな思いで一年前従兄の幸平の口づけを受けた。あの日は幸平の家の大欅で蝉時雨が空を砕いてしまいそうに啼いていた。
この地方では、その平野で取れる米で麹を作り、その麹と大豆で味噌を仕込んだ。各家では畑で収穫した大豆を、米麹の加工業者に頼み、大豆を発酵させてもらう。豆を発酵させることを、この近辺の人々は大豆に花をつけると、呼んでいる。
洗って一晩水につけた大豆を蒸籠のお化けのような巨大な甑に入れる。水をたっぷり入れた大釜を竃に設え、大釜の上に藁で編んだドーナツ形の甑藁を置いて、大豆の入った甑を据える。薪で釜の水を沸かして大豆を蒸すのである。蒸した大豆は筵に広げて酵母菌を振り入れる。酵母菌の付着した大豆を麹蓋にいれて、その日の温度加減によって一日あるいは二日室で寝かせると、大豆はきれいな黄色の花をつける。