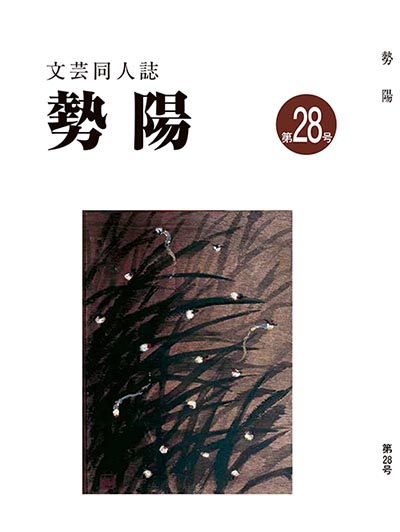
随筆
『青カビ大根』
P124-126
直腸ガンで残り三カ月を宣告されたとき、
「わたしの母は百歳まで生きました。だからわたしも百歳まで生きます」
先生と向かいあう診察室で、矢島さんは大声でそう叫んだ。
彼の母が腹膜炎を患ったのは戦争直後の昭和二十年代が終ろうとする頃、つまりは米麦はいうに及ばず味噌醤油から砂糖にいたるほとんどの食料品が、配給という否応ない手段に頼るほかない時代だったから、タンパク質やビタミンを十分に補給することなど不可能に近かったのである。
タンパク質を補給するためには、近くの川で捕えた魚や牛蛙をさばいて小麦粉にくるんで炒めたものを食べるより他なく、食べることすらがそれほどに困窮した時代だったから、病気にかかって高価な薬品に頼ることなど思いのほかだったのである。
母が腹膜炎にかかったとき、矢島さんは打つ手を失って、先ずは近所の祈祷師に相談すると、
「彼岸花の球根がいい。水に晒して煎じればいい」
そんな助言をしてくれた。
外へ出ると雨蛙が鳴いていて、彼岸花などどこにも見当たらない。途方にくれながら田圃の土手をたどって手当たりしだい掘り返してみると、なんのものかはわからない球根二十個ほどを掘り当てた。
近くの笛吹川で洗い、五日間水に晒してあく抜きをしたあと、彼はそれを煎じて母に飲ませた。
結果は病状が好転することはなく、下痢と発熱がつづいて母の病状は悪化するばかり。体は日々に痩せ細って絶え間ない唸り声をあげ、あきらかに命にかかわる状態となって、やむなく貴重な米一升を売って金に換え、国立明星病院に受診する決心をした。
− 124 −
診察を担当してくれたのは、満洲から帰国して間のない藤田先生だった。
診察する先生の指先が右季肋部を抑えると、
「痛い!」
母は唸り声をあげた。
同じ場所を小さく叩くと、
「やめて!」
大声をあげる母に向かって、
「腹膜炎ですね」
先生は容赦なくそう宣告し、
「ペニシリンを打つほかはない」
そう断定したのである。
「ペニシリン?」
聞いたことのない薬の名を耳にして、たじろぐ矢島さんに、
「ペニシリンはアメリカからの輸入薬品でな……」
そういった後、注射一本の代金が米一俵に相当することを話した。当時の米一俵は
一万二千円、サラリーマンの一カ月の給料に相当する金額だった。百姓一本で暮らしをたて、育ち盛りの子供十
人をかかえているのである。
驚愕する矢島さんの表情を見てとりながら、
「ペニシリンの素材は青カビからつくられている」
先生は独り言のようにいい、
「その青カビを集めればいい」
とつぶやいた。
「蜜柑の皮、どこかにないかな」
ぽつりとつぶやくのへ、
「夏に蜜柑などありません」
困り果てて返した矢島さんに、
「そうだ、干し大根がある。このあたりは伊勢沢庵の産地だからな。それを探そう。干し大根についたアオカビ、それを探そう。そしてそれを飲むんだ。それを飲んだ後は、ひたすら神に祈るほかはない」
先生は確信を得たかのようにそういったのである。
矢島さんにはペニシリンが何なのか青カビが何なのかなどまるで見当もつかない話だったが、その青カビが薬の素材であり、母の難病と戦ってくれるはずの薬剤だろうという朧気な理解はあったが、
「青カビ、そのまま飲んで効くんですか」
思わずそう口ずさみながら、それでも一万二千円を支
− 125 −
出してペニシリンを打つより、まずは青カビを探すことから始めるより術はない、心中でそう叫んでいた。
その日から、矢島さんは周辺の町村を廻って農家という農家、漬物屋という漬物屋を訪ねてまわってことの次第を話し、青カビを探した。
青カビが手に入ったのは十日後、
「ほう、青カビが薬になあ」
驚きの顔をみせながらも、青カビの生えた大根をどさりと手渡してくれたのは漬物屋だった。それを明星病院に運んで先生にみせ、青カビを集める方法から煎じ方までを教わって母に飲ませることができたのはさらに三日がたってからだった。
先生の言葉を信じることが出来たのは、青カビを飲ませて五日目がたった頃、熱が下がったからだった。六日には下痢が治まり、七日が経つと食べ物が喉を通るようになった。
青カビの効力に驚き、それを提案してくれた先生への感謝を胸に納めながら、配給の缶詰を闇でさばいてお礼の品を買い、青カビを教えてくれた明星病院の藤田先生を訪ねたのはさらに一週間が経ってからだった。
「すごい!」
目をうるませながら、母の回復に感動の声をあげたのは先生のほうだった。
診察室で向かいあう先生に、
「わたしも百歳まで生きます。青カビ大根を頭に描きながら、かならず母のように百歳まで生きます」
天寿を全うした母の俤を頭に描きながら、矢島さんは確かな口調でそういった。
おわり
− 126 −